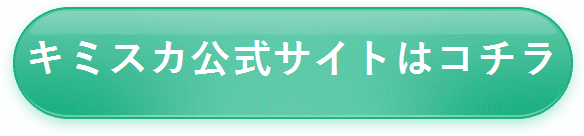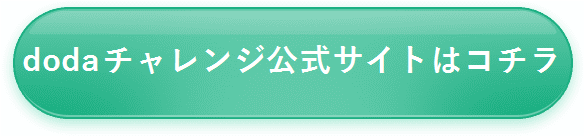dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します


dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と言われるのはどうして?
dodaチャレンジに登録したのに、「紹介できる求人がありません」と言われてしまった…そんな残念な経験をされた方もいるかもしれません。せっかく転職に前向きになったのに、いきなりお断りされてしまうとガッカリしますよね。でも、落ち込む前に知っておきたいのが、断られるのには理由があるということ。dodaチャレンジの仕組みや企業側の状況を理解すれば、次のステップに向けて準備を整えることができます。この記事では、「なぜ求人紹介が受けられないのか?」という疑問にお答えしながら、断られやすい人の特徴や、その対策についても詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、dodaチャレンジで断られる理由と、その対処法がよく分かります。
dodaチャレンジで断られる主な理由

どうして求人を紹介してもらえないの?何が影響しているの?
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえないケースには、いくつかの共通する理由があります。サービス側の制約だけでなく、利用者側の条件や状況によっても左右されるのです。以下はよくある断られる理由です。
- 希望条件が厳しすぎる
- スキルや職歴が不足している
- 求人が少ないエリアに住んでいる
- 精神障害者の受け入れに消極的な企業が多い
たとえば「完全在宅勤務のみ」「年収○○万円以上」「通勤時間は30分以内」といった細かい条件を指定すると、該当する求人が極端に少なくなってしまいます。また、過去の職歴が浅かったり、就業ブランクが長かったりすると、マッチする求人が見つかりにくくなります。さらに、地方在住の場合は都市部に比べて求人そのものが少ないため、紹介が難しくなることもあります。

紹介されない背景には、希望条件やスキル、居住地、障害の内容など複数の要因があるんですね。
断られないための対策

どうしたら紹介される確率を高められるの?
dodaチャレンジで断られないようにするためには、こちら側の準備もとても大切です。以下のポイントを意識することで、紹介される可能性をグッと高められます。
- 希望条件を柔軟に見直す
- 必要なスキルや資格を身につける
- 職務経歴書や自己PRを丁寧に仕上げる
- 他の就職支援サービスも併用する
条件の柔軟さを持つことはとても重要です。こだわりすぎず、「どんな働き方でもまずは経験を積みたい」というスタンスがあると、企業側も安心して紹介できるようになります。また、スキル面ではパソコン操作やビジネスマナーの基礎を習得しておくだけでも印象は大きく変わります。

「紹介されやすい人」になるためには、ちょっとした工夫と柔軟性がカギなんですね。
もし断られたらどうすればいい?

実際に断られてしまったら、次はどう動けばいいの?
断られたとしても、それで終わりではありません。その後の行動がとても大切です。自分の経歴や条件を見直し、他の選択肢も検討していきましょう。
- 他のエージェントを利用する
- 就労移行支援を検討する
- 自己分析を深める
たとえば、就労移行支援事業所を利用すれば、職業訓練や面接対策など、就職活動全般を支援してもらえることもあります。断られた理由を前向きに捉えて、新しい方向へ踏み出しましょう。

断られても、視点を変えて動けばいくらでもチャンスは見つかります!

dodaチャレンジで断られる理由が分かれば、次に取るべき行動が見えてきます。あきらめず、自分に合った道を探しましょう!
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない

条件や地域の希望があると、求人が見つからないことがあるの?
dodaチャレンジでは、求職者の希望と企業側の条件がマッチしないと、「紹介できる求人がありません」と案内されることがあります。とくに次のようなケースでは、求人が見つからず断られてしまう可能性が高くなります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
在宅勤務のみや高年収などの条件を設けると、そもそも求人自体が少ないのが現実です。特に障がい者雇用枠では、企業側にも配慮の必要があるため、条件が厳しいと紹介が難しくなります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
特定の業種・職種に絞りすぎると、該当する求人が非常に少なくなり、dodaチャレンジでも紹介のしようがないことがあります。幅広い選択肢に目を向けるのも一つの方法です。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方は求人そのものが少ない傾向があり、勤務地の選択肢を限定しすぎると、結果的に紹介できる求人が見つからなくなることがあります。

柔軟な条件設定が求人を見つけやすくするポイントですね!
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合

dodaチャレンジのサポート対象にならない人もいるの?
サポートを受けられないケースもあります。dodaチャレンジは障がい者雇用に特化した支援を行っているため、条件に合わないと判断されると対象外となることがあります。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠での求人紹介は、原則手帳が必要)
障がい者雇用枠での紹介を受けるためには、障がい者手帳の所持が原則条件。未取得の状態ではサポート対象にならない可能性が高いです。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
ブランクが長いと、就労の継続が難しいと判断されることがあり、紹介に結びつかないケースがあります。
体調が不安定で、就労が難しいと判断される場合
現在の体調が安定していない場合は、まず就労移行支援などを提案されることもあります。

体調や手帳の有無など、基本的な条件が整っていないと紹介は難しいんですね。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合

面談の印象や準備も結果に影響するの?
dodaチャレンジでは面談を通して求人紹介の可否が判断されます。以下のような準備不足や説明不足があると、求人の紹介が難しくなる場合があります。
障がい内容や配慮事項が説明できない
企業が働きやすい環境を用意するためには、適切な情報提供が必要です。自分にとって必要な配慮を具体的に説明できることが大切です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
自分がやりたいことが見えていないと、紹介される求人の幅も狭くなってしまいます。
職務経歴がうまく伝わらない
自己紹介やこれまでの経歴を整理しておかないと、エージェントも適した求人を提案しにくくなります。

事前準備をしっかりすることで、より良い紹介につながるんですね!
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました

実際に断られた人たちは、どんな理由でdodaチャレンジに断られたんだろう?
体験談1・軽作業派遣とタイピングしか経験がない
障がい者手帳は持っていたものの、職歴は軽作業の派遣のみで、PCスキルはタイピング程度。資格も特になかったため、「紹介できる求人がありません」と案内されてしまったとのことです。
体験談2・就労可能な状態に見えなかった
エージェントから「継続的に働ける状態ではない」と判断され、「まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を受けるように」と提案されたとのこと。
体験談3・長期のブランクがネックになった
精神疾患で10年以上療養していた方がdodaチャレンジに相談したところ、「就労経験のブランクが長く、まずは体調安定と訓練を」と言われたそうです。
体験談4・地方+専門職希望で該当求人なし
四国の田舎町で在宅ライターやデザイナー職を希望していた方は、「ご希望に沿う求人は紹介できません」と断られました。
体験談5・正社員経験がなく、紹介されなかった
アルバイトや短期派遣ばかりで正社員経験がゼロだったため、「現時点では正社員求人の紹介は難しい」と案内されたケースです。
体験談6・条件が多すぎてマッチする求人がなかった
子育て中の方で、「完全在宅・週3勤務・時短・事務職・年収300万円以上」と希望条件を出した結果、「ご希望すべてを満たす求人は紹介できない」と断られました。
体験談7・障がい者手帳を持っていない
精神障がいの診断を受けているが手帳未取得のため、「手帳がないと紹介が難しい」と言われ、登録は受け入れられませんでした。
体験談8・未経験で専門職希望だった
長年軽作業をしていた方が、体調面を考慮して在宅のITエンジニア職に挑戦しようとしたところ、「未経験では紹介が難しい」と断られました。
体験談9・在宅で短時間勤務しか難しい
身体障がいで通勤が困難、週5勤務も無理という状況で短時間の在宅勤務を希望したが、「紹介できる求人がありません」と断られたとのことです。
体験談10・高すぎる条件でマッチする求人がなかった
前職では一般職だったが、今回は管理職・年収600万円以上の障がい者雇用を希望。dodaチャレンジからは「ご紹介可能な求人はありません」と回答されたそうです。

体験談から分かるのは、条件や状況に応じた柔軟な対応が大切ということですね。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します

もしdodaチャレンジで断られたら、どうやって立て直せばいいの?
せっかく転職活動に踏み出したのに、dodaチャレンジから「求人を紹介できません」と断られてしまうと、「自分には可能性がないのかも…」と不安になる方も多いと思います。でも安心してください。断られたからといって、転職のチャンスが完全に絶たれたわけではありません。大切なのは、なぜ断られたのかを理解し、適切な対処法を知ることです。
スキル不足やブランクの長さ、体調面の不安、希望条件の厳しさ…。こうした要因が理由で断られてしまった場合でも、やり方次第で次のチャンスにつなげることができます。ここでは、具体的なケースに応じた対策を詳しく紹介していきますので、自分に合った方法を見つけて、前向きに次のステップへ進みましょう。

断られたときこそ、自分を見つめ直して次に活かすチャンスですね!
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について

スキルや経験が少ないときは、どうやって再挑戦すればいいの?
dodaチャレンジでは、職歴が浅い・PCスキルに不安があるなどの理由で、求人を紹介してもらえないケースもあります。でも、だからといって諦める必要はありません。自分をレベルアップさせる方法はたくさんあるんです!以下のような方法で、確実に前進することができますよ。
ハローワークの職業訓練を利用する
ハローワークでは、PCスキル(Word・Excel・データ入力など)を無料または低価格で学べる職業訓練が充実しています。事務系の仕事に挑戦したい方には特におすすめで、履歴書にも書けるスキルが身につきます。
就労移行支援を活用する
ビジネスマナーや職場でのコミュニケーション、報連相などを身につけながら、安心してスキルアップできるのが就労移行支援。メンタルのケアも受けられるので、初めての就活でも不安が少なくなります。
資格を取る(MOSや日商簿記など)
資格を持っているとスキルの証明になり、自信にもつながります。特にMOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級などは事務職に強く、おすすめです。

職歴が浅くても、スキルや資格を身につけることでチャンスは広がりますね!
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について

長いブランクがあると不利って聞くけど、どう対処すればいいの?
「長く働いていなかったから…」と不安になる方も多いですが、しっかり準備をすれば再スタートは可能です。ブランクがあっても、自分に合ったステップを踏むことで道は開けます。焦らず、確実に前へ進みましょう。
就労移行支援を利用して生活リズムを整える
毎日通所して活動するだけでも、生活のリズムが整います。プログラムを通して実務的なスキルや就労実績を積めるので、再挑戦の足がかりになります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る
いきなりフルタイムは難しい…そんなときは、週1〜2日からの短時間バイトや在宅業務がおすすめ。少しずつ働けることを証明することで、信頼と実績を得られます。
実習やトライアル雇用に参加する
企業実習やトライアル雇用では、実際の業務に携われる貴重なチャンスです。この経験があれば、再度dodaチャレンジに登録する際にも有利に働きます。

ブランクがあっても、一歩ずつ準備すれば就職への道は必ず見つかります!
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について

地方に住んでいても、求人を見つける方法はあるのかな?
都市部に比べて地方では、障がい者雇用枠の求人自体が少ないのが現実です。また、最近はリモートワークの希望者も増えていますが、障がい者雇用でのフルリモート求人はまだまだ限定的。そんな状況でも、方法次第で可能性を広げることができます。
在宅勤務OKの求人を探す(複数のエージェントを併用)
在宅勤務を重視する場合は、dodaチャレンジ以外の障がい者専門エージェントも利用してみましょう。特に、在宅ワークに特化した「atGP在宅ワーク」や、サポートが手厚い「サーナ」「ミラトレ」などを併用すると、求人の幅が広がります。
クラウドソーシングで在宅実績を作る
「ランサーズ」や「クラウドワークス」など、クラウドソーシングを活用すれば、ライティングやデータ入力などの仕事を在宅で始められます。実績を積むことで、将来的に在宅正社員の道も見えてくるかもしれません。
地域の支援機関に相談する
地元に根ざした求人を探すには、ハローワークや障がい者就労支援センターが頼れる存在。大手エージェントに出ていない求人が見つかることもあり、意外なチャンスに出会えることもあります。

他サービスの併用や地域機関の活用で、地方でもチャンスはしっかり見つかります!
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について

希望条件をたくさん出しすぎると、求人が見つからなくなるの?
「完全在宅」「週3勤務」「年収◯万円以上」など、こだわりが強くなるほど、マッチする求人が少なくなってしまう傾向があります。dodaチャレンジでは条件に合う求人がないと、紹介を断られるケースも珍しくありません。でも、少し条件を見直すだけで、転職の可能性を広げることができるんです!
条件に優先順位をつける
まずは「どうしても譲れない条件」と「できれば希望したい条件」を整理しましょう。全部を叶えようとすると求人の数が激減してしまうので、まずは譲れるポイントを明確にしておくと、紹介される可能性がグッと高まります。例えば、「完全在宅が理想」でも「週1〜2日なら出社も可能」といった柔軟さが大切です。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する
条件を見直して、再度dodaチャレンジのアドバイザーに相談してみましょう。「勤務時間は1日6時間が限界」「月1出社までならOK」など、具体的に伝えることで、よりマッチする求人を探してもらいやすくなります。一度断られたからといって、再チャレンジできないわけではありません!
段階的にキャリアアップする戦略を立てる
最初は理想より少し条件を緩めてスタートし、スキルアップや経験を積みながら希望の働き方に近づけていくというのも賢い方法です。たとえば、「まずは短時間勤務で慣れ、ゆくゆくはフルタイムへ」「一般事務から始めて専門職を目指す」など、自分に合ったステップを踏んでいきましょう。

条件を整理して柔軟に考えることで、希望の働き方に一歩ずつ近づけますね!
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について

障がい者手帳を持っていないと、求人紹介を受けるのはやっぱり難しいの?
dodaチャレンジでは、障がい者雇用枠の求人紹介が中心となるため、障がい者手帳の有無が一つの判断基準になります。ですが、手帳がなくてもあきらめる必要はありません。状況に応じた対処法を取ることで、就職のチャンスをつかむことができます。
主治医や自治体に手帳申請を相談する
精神障がいや発達障がいの方でも、一定の条件を満たせば手帳の取得が可能です。まずは主治医に相談し、申請が可能かどうかを確認しましょう。自治体の福祉課でも詳しい説明を受けられます。手帳を取得することで求人の幅が広がるため、前向きに検討してみるのもおすすめです。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す
手帳がなくても就職は可能です。ハローワークでは「手帳不要」の求人を扱っていることがあり、一般枠での就職も視野に入れることで選択肢が広がります。また、就労移行支援を経てスキルを磨き、将来的にdodaチャレンジを再活用するという流れも有効です。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する
無理に就職を進めるよりも、まずは体調を整えることが重要です。安定してから手帳取得を目指し、再度転職活動に臨めば、より良い条件での就職が実現しやすくなります。

手帳がない場合でも、体調を整えたり他の支援制度を使うことで就職の道は広がりますね!
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する

dodaチャレンジ以外にも使えるサービスってあるの?
dodaチャレンジで断られてしまったとしても、就職のチャンスが消えるわけではありません。他にも多くの転職支援サービスやサポート機関があるため、一つのサービスにこだわらず視野を広げることがとても大切です。
たとえば、障がい者向けエージェントの「atGP」「サーナ」「ラルゴ高田馬場」などは、それぞれに異なる強みがあり、自分に合った支援を受けられます。また、地域の障がい者就労支援センターやハローワークでは、地元の求人を紹介してもらえることもあります。
大切なのは、「ここでダメだったから終わり」ではなく、「他に道がある」と気持ちを切り替えること。複数のサービスを活用しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。

一つのサービスで断られても、他に選択肢があると前向きになれますね!
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します

精神障害や発達障害があると、dodaチャレンジでは求人紹介が難しいって本当?
dodaチャレンジに登録してみたものの、「ご紹介できる求人がありません」と断られてしまった経験を持つ方もいるかもしれません。特に精神障害や発達障害があると、「自分の障害特性が理由で不利なのでは?」と不安になることもありますよね。
確かに、dodaチャレンジでは障がいの種類や等級、体調の安定度、希望条件によっては、求人の紹介が難しくなることがあります。精神・発達障害の方は配慮が必要な点が多いため、マッチする求人の数が少なくなることがあるのは事実です。
しかし、これは決して「就職できない」という意味ではありません。むしろ、自分の特性に合った職場や働き方を見つけやすくなるようサポートしてくれる仕組みがあるのです。この記事では、身体障害者の就職と比較しながら、精神・発達障害の方がdodaチャレンジをうまく活用する方法について詳しく解説していきます。

精神・発達障害があっても、ポイントを押さえればdodaチャレンジの活用は十分可能なんですね!
身体障害者手帳の人の就職事情について

身体障害があると、就職はしやすい傾向にあるって本当?
身体障害者手帳を持っている方は、企業側にとって配慮すべきポイントが明確なため、就職におけるハードルが比較的低いと言われることがあります。もちろん、障害の内容や業務内容によっては制限もありますが、特性が明確で対応が取りやすい分、企業が安心して採用しやすい傾向があるのは事実です。
障害の等級が軽度であれば求人に応募しやすい
等級が5級や6級といった軽度であれば、幅広い職種に応募が可能です。事務職や軽作業といった負担の少ない仕事に就きやすく、企業側も受け入れのハードルが下がります。
障がいの内容が「見えやすい」ため配慮がしやすい
身体障がいは視覚的に分かりやすく、また診断書などでも明確に示されるため、企業がどのような配慮をすればよいかが把握しやすいというメリットがあります。
合理的配慮の内容が具体的で、企業側も対応しやすい
バリアフリー化、補助器具の提供、業務内容の調整など、具体的な配慮が取りやすいことから、企業も安心して雇用を進めることができます。
通勤・作業に制限があると選べる求人は限られる
一方で、移動が難しい場合や、手作業を伴う仕事ができない場合など、障害によっては求人の選択肢が限られてしまうケースもあります。
コミュニケーションが問題なければ一般職にも挑戦できる
身体的な障がいがあっても、円滑なコミュニケーションが可能であれば、営業や事務などの一般職に応募できるチャンスも十分にあります。
PCを使った仕事は求人が多く、採用されやすい
身体障がい者向けの求人では、事務職やデータ入力などのPC業務が多く見られます。身体への負担が少なく、在宅勤務が可能な求人もあるため、働き方の幅が広がります。

身体障がいの方は、配慮内容が明確だからこそ、企業も採用しやすいんですね!
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について

精神障害者手帳があると、就職にはどんな影響があるの?
精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、身体障がいの方と比べると就職のハードルがやや高くなる傾向があります。これは、障がいの特性が見えにくく、企業側が「どう配慮すればいいか」判断しづらいからです。
症状の安定性と継続勤務がカギになる
企業が最も重視するのは、安定して働けるかどうかです。就労歴にブランクがある場合や、休職・離職が多いと不安視されることがあります。通院や生活リズムの安定が就職の第一歩になります。
見えない障がいだからこそ、企業に伝えることが重要
外見から分かりにくい精神障害は、企業にとっては「配慮の必要性」が見えづらいことがネックになります。面接時には、自分の特性とそれに対する配慮内容を具体的に説明することが大切です。
配慮の伝え方が採用の分かれ道に
例えば、「静かな作業環境があると集中しやすい」「文字での指示があると助かる」など、現実的で受け入れやすい配慮を提示することで、企業も対応しやすくなります。求めすぎないことも重要です。

自分に必要な配慮を伝える力が、精神障がいのある方の就職成功のカギですね!
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について

療育手帳のA判定とB判定では、就職のしやすさが変わるの?
療育手帳を持っている方の場合、A判定(重度)かB判定(中軽度)かによって、就職の選択肢が大きく変わります。それぞれに合った就労環境や支援制度を活用することで、無理のない働き方が可能になります。
A判定は福祉的就労が中心
A判定の方は、就労継続支援B型などの福祉サービスを通じて働くケースが多く、作業スキルを無理なく身につけられる場が用意されています。
B判定なら一般就労も視野に入る
B判定であれば、軽作業系の求人や事務補助、清掃業務などで一般就労を目指すこともできます。支援者やアドバイザーと一緒に、自分に合った職種を見つけていくのがポイントです。

等級に応じた支援を活用することで、療育手帳を持つ方も無理なく働くことができますね!
障害の種類と就職難易度について

障がいの種類によって、就職のしやすさってどれくらい違うの?
障がい者雇用の現場では、障がいの種類によって企業側の対応しやすさが異なるため、就職のしやすさにも違いが出てきます。一般的には、配慮が明確で分かりやすい障がいほど、企業が受け入れやすく、就職のハードルも下がる傾向にあります。
身体障がい(特に軽度)は、必要な配慮が具体的で明確なため、企業が採用しやすいとされます。一方で、精神障がいや発達障がいは、見た目ではわかりづらく、企業側に理解や柔軟な対応が求められるため、就職の難易度がやや高くなります。
また、知的障がいを持つ方は、手帳の区分(A判定・B判定)によって就労可能な範囲が異なります。A判定の場合は福祉的就労が中心ですが、B判定なら一般就労も目指しやすくなります。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく福祉就労が中心になる傾向 |

障がいの特性に合わせた対策をとることで、どんな手帳でも就職の可能性は広がりますね!
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて

障害者雇用枠と一般枠って、どう違うの? どっちを選べばいいの?
障がいのある方が就職を考える際には、「障害者雇用枠」か「一般雇用枠」のどちらに応募するかを選ぶ必要があります。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った働き方が見つけやすくなります。
障害者雇用枠の特徴
- 企業が法的義務に基づいて設置した枠
- 雇用率制度(2024年4月から2.5%以上)により、一定の割合で採用される
- 障害をオープンにして、配慮事項を伝えることが前提
一般雇用枠の特徴
- 障害の有無にかかわらず、すべての応募者が同条件で選考される
- 障害の開示は任意(オープン or クローズ就労を選べる)
- 基本的に配慮や特別措置は受けられない
どちらを選ぶかは、自分の体調や障がい特性、希望する働き方によって変わってきます。配慮が必要な場合は障害者雇用枠、スキルで勝負したい方は一般枠という選択もあります。

自分にとって無理のない選択をすることが、就職活動成功の第一歩ですね!
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか

年齢が上がると、やっぱり障がい者雇用でも就職しにくくなるの?
障がい者の就職事情は、年齢によって採用の難易度が異なることがあります。特に20代〜30代の若年層は、未経験OKの求人も多く採用されやすい傾向があります。一方で、40代・50代以上になると、職務経験やスキルがより重視されるため、就職活動が難しくなるケースも出てきます。
年代ごとの傾向を把握して、自分の強みを活かした就職活動をすることが大切です。以下は、年代別の雇用状況をまとめたものです。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
|---|---|---|
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職や転職が中心。未経験OKの求人が多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指した転職が多く、経験者枠が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で選択肢は広がるが、未経験職種はやや厳しい |
| 50代 | 約10~15% | 求人は少なめだが、専門職や経験を活かした採用が中心 |
| 60代 | 約5% | 嘱託や再雇用、短時間勤務などがメインの働き方 |
年齢が高くなるにつれ、求人数は少なくなりますが、PCスキルや専門スキルを身につけることで、採用の可能性を高めることは十分に可能です。在宅勤務や業務特化型の求人など、自分の強みに合わせた働き方を見つけるのがポイントです。

年齢に合わせた戦略を立てることで、どの年代でも就職のチャンスは広がります!
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか

年齢が上がると、やっぱり障がい者雇用でも採用されにくくなるのかな?
障がい者の雇用状況は年代によって大きく異なり、一般的には若年層ほど採用されやすく、年齢が上がるほど就職が難しくなる傾向があります。これは、企業側が若手人材を長期的に育成したいという意向や、未経験OKの求人が多い点などが背景にあります。
若年層(20〜30代)は求人も多く採用率が高め
20代〜30代は、企業が将来を見据えた人材として採用しやすい年代です。未経験でも挑戦しやすい職種が多く、成長ポテンシャルを重視した採用が行われています。特に、就労移行支援などでスキルを身につけた人材は、事務系や軽作業系などの幅広い分野で活躍しやすくなります。
40代以上はスキル・経験の有無が大きなカギに
40代以降になると、企業が即戦力を求める傾向が強まり、スキルや実績が求められることが多くなります。未経験職種へのチャレンジは難しくなるため、これまでのキャリアを活かした職種や、自分の得意分野に絞った就職活動が効果的です。
50代以上は短時間勤務や限定業務が中心
50代を過ぎると、求人はぐっと少なくなり、短時間勤務や特定業務に限定されることが増えてきます。体力的な面も考慮され、清掃、軽作業、在宅事務などが中心に。PCスキルや資格があれば、在宅ワークなどの選択肢も広がります。

どの年代でも、スキルや得意分野を活かせば就職のチャンスはありますね!
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?

就活エージェントって、年齢によって利用できないことってあるのかな?
障がい者向けの就活エージェント、たとえばdodaチャレンジなどを利用する際、「年齢が高いと断られてしまうのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。実際のところ、公式に年齢制限が設けられているわけではありませんが、求人の傾向として年齢層のターゲットがあるのが実情です。
年齢制限は明記されていないが、50代前半までが中心
dodaチャレンジを含め、多くのエージェントでは50代前半までの求職者をメインターゲットとしています。理由は、企業が「長く働いてくれる人材」を重視しているため。そのため、50代後半や60代以上の方にとっては、求人の選択肢が少なくなる傾向にあります。
ただし、経験やスキルを活かした職種、または短時間勤務のような働き方であれば、年齢に関係なく活躍できる場もあるため、他の就職支援機関と併用しながら活動するのが効果的です。
ハローワークや障がい者職業センターの併用が効果的
年齢が高くなって求人紹介が難しくなる場合には、ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の活用も視野に入れましょう。
これらの公的機関では、年齢に関係なく求人を紹介してくれるだけでなく、職業訓練や職場実習の機会も提供されています。未経験の仕事に挑戦したい方や、再スタートを切りたい方には心強い支援となります。
エージェントと公的機関の併用によって選択肢が広がるので、柔軟に就職活動を進めていきましょう。

年齢にかかわらず、公的支援を活用すれば就職チャンスは十分にあります!
dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問

dodaチャレンジって実際どうなの?評判や体験談が気になるなあ。
dodaチャレンジを検討している方の中には、「本当に自分に合っているサービスなのか?」「登録しても求人がなかったらどうしよう…」と不安を抱えている人も多いかもしれません。
ここでは、dodaチャレンジに関するよくある質問を分かりやすくまとめて解説します。あわせて、詳しく知りたい方のために関連ページのリンクも紹介していますので、気になる項目があればぜひチェックしてみてください。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの利用者からは、「求人の紹介がスムーズだった」「カウンセリングが丁寧だった」といった好意的な意見がある一方、「希望する求人がなかった」「面談後に連絡が来なかった」といった指摘も見られます。
実際の口コミや評価の詳細を確認したい方は、以下の関連ページをご覧ください。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミをチェック!障害者雇用の特徴やメリット・デメリットを解説
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と言われたり、登録自体を断られてしまうことがありますが、原因を見極めて対処すれば再チャンスを掴めることも多いです。
例えば、スキル不足が理由なら職業訓練の受講や、他の障がい者専門エージェントとの併用が効果的です。以下のリンクから、具体的な対処法をチェックしてみてください。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた人続出?理由や対処法、難しいと感じた体験談を紹介!
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡がない場合、求人のマッチングが難航している、企業との調整に時間がかかっている、または連絡の行き違いなどが原因として考えられます。
心配な場合は、こちらから状況を確認する連絡をしてみるのも良いでしょう。詳細な事例や対応方法は、以下のページをご覧ください。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なし?考えられる理由と対処法|面談・求人・内定のケース別に解説
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、これまでの職務経験や希望条件、障がいの特性、働くうえで必要な配慮などについて細かくヒアリングされます。
あらかじめ話したい内容を整理しておくと、面談がスムーズに進みやすくなります。流れや聞かれる内容を知っておくと安心して臨めますよ。
関連ページ:dodaチャレンジ面談突破ガイド:内定獲得への流れ、注意点・対策・準備を徹底解説!
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者のための転職エージェントサービスです。登録すると専任のキャリアアドバイザーが付き、希望やスキルに合った求人を紹介してくれます。
求人紹介だけでなく、応募書類の添削や面接対策、企業との面談調整まで幅広いサポートが受けられるため、転職活動が不安な方にも心強いサービスです。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジでは、基本的に「障がい者雇用枠」での求人紹介が中心となっているため、手帳がない場合は利用が難しくなることがあります。
ただし、手帳の取得を検討している場合や、取得に向けて準備中であることを伝えることで、アドバイザーからアドバイスを受けられることもあります。まずは相談してみるのがよいでしょう。
関連ページ:dodaチャレンジは手帳なしでも使える?障害者手帳は必須?申請中の利用条件を解説
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類に関わらず基本的に登録が可能です。ただし、登録できたとしてもサービスの対象外と判断されることがあります。
たとえば、長期間のブランクや職歴が極端に少ない場合、または体調面で安定して就業が難しいと判断される場合は、就労移行支援など他のサービスを勧められることがあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
退会を希望する場合は、担当のキャリアアドバイザーに直接連絡をするか、dodaチャレンジの公式サイト内にあるお問い合わせフォームから退会手続きを依頼できます。
スムーズに退会するためにも、事前に今後の転職活動の方針を整理しておくと安心です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
基本的にはオンラインでの実施が主流で、電話やWeb面談を通じてカウンセリングを受けることができます。
対面での面談を希望する場合は、対応可能な拠点があるかどうか事前に確認することをおすすめします。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには明確な年齢制限は設けられていませんが、実際には20代〜50代前半が主な対象層となっています。
50代後半以降の方は、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターを併用することで、より多くの求人に出会える可能性があります。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、離職中の方でもdodaチャレンジに登録して転職支援を受けることが可能です。
ただし、直近の職歴がない、またはブランクが長い場合は紹介される求人が限られることもあるため、スキルアップや訓練などの準備も併せて検討することをおすすめします。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは主に「転職者」を対象としているため、新卒向けの求人が少なく、学生の利用は難しいケースがあります。
学生の方は、大学のキャリアセンターや、新卒向けの障がい者支援サービスの利用も併せて検討してみてください。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較

dodaチャレンジって、登録すれば必ず求人を紹介してもらえるの?他のサービスと何が違うんだろう?
「障がい者向けの就職サービスを使ってみたいけど、本当に自分に合った求人を紹介してもらえるのかな?」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職支援サービスですが、求職者のスキル・体調・希望条件などによっては、求人紹介が難しい場合もあります。しかしこれは、dodaチャレンジに限った話ではなく、他の障がい者就職サービスでも同じような傾向があります。
では、dodaチャレンジと他のサービスには、どのような違いがあるのでしょうか?それぞれの特徴を比較しながら、自分に合った就職支援サービスを選ぶためのヒントを紹介していきます。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
|---|---|---|---|
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー (atGP) |
1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビ パートナーズ紹介 |
350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援 ミラトレ |
非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッド チャレンジ |
260 | 東京、神奈川、 千葉、埼玉、大阪 |
全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、 東海、福岡 |
全ての障害 |

各サービスの違いを理解して、自分に合った支援を選ぶことが転職成功への第一歩です!
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ

結局、dodaチャレンジで断られた場合って、どうすればいいの?他にも使えるサービスってあるのかな?
dodaチャレンジは障がい者雇用に特化した転職エージェントで、多くの利用者にとって心強いサービスですが、必ずしもすべての人に求人が紹介されるわけではありません。「希望条件が厳しすぎる」「スキルや職歴が不足している」「体調が不安定」「障がい者手帳が未取得」など、さまざまな理由で断られるケースがあります。特に、地方在住で完全在宅勤務のみを希望する方や、ブランクが長い方は、紹介が難しくなる傾向にあります。ですが、これはdodaチャレンジだけに限らず、他の障がい者向け転職支援サービスでも起こり得ることです。
重要なのは、断られた理由を理解し、スキルアップや条件の見直し、他のエージェントの併用など、前向きな対処を取ることです。「atGP」や「サーナ」「ミラトレ」など、在宅勤務に強いサービスや、地域密着型のハローワーク、障がい者職業センターの活用も選択肢のひとつです。就労移行支援を通じて就労準備を整え、再度チャレンジするという方法もあります。
本記事では、dodaチャレンジでの断られた理由や体験談、対処法を幅広く解説しました。「自分はダメだった…」と落ち込まずに、自分に合った方法を模索し、焦らずに一歩ずつ前進していきましょう。

諦めずに、環境や方法を変えて再挑戦することが大切です!